![]()
有限会社ヤマカ木材
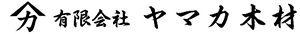
林業
当社は日本では珍しくなった架線系システムを使った森林整備を行っています。
森林は水と空気を生み出す生活の基盤です。
間伐遅れによる森林の荒廃が進まぬよう、技術力を高め、競争力のある林業を目指します。
当社が位置する木曽谷南部はかなり急峻な地形であり、全国的に主流で生産性が高いといわれる「車輛系システム」がほぼ使用できません。
代わりに使用される「架線系システム」は現在採用している地域が少なく、習得に時間のかかる難しい技術です。
現在森林整備が遅れている場所は「架線系システム」が必要になるような条件の厳しい山奥であることが多いです。
我々は、この「架線系システム」の改良を行うことで今まで森林整備を行いにくかった地域の森林環境を改善する道筋を探そうとしています。
- 住所
- 長野県木曽郡南木曽町読書2435-2
- 地域
- 木曽
- 主な取組内容
-
SDGs達成に向けた経営方針等
当社を含む勝野木材グループの経営理念として「持続可能な森林経営を通じて、【社会貢献】し続ける企業を目指すと同時に、全社員の幸せを実現する。」を掲げており、それはSDGsの理念と重なる部分が大きい。SDGsの枠組みを利用することにより、社員の知識・価値観を高め、持続可能な社会により一層貢献していくことを目指す。
重点的な取組1
- 環境
内容
持続的な森林整備を通じて地域及び下流域の生活環境と水資源を守る
また、持続可能な資源である木材の利用を推進するため、市場に原木を安定的に供給する。
2030年に向けた指標
年間の間伐量100ha以上を維持する
環境負荷を生じない施業方法で、木材生産量年間25,000㎥を目指す。
現状、国有林の施業が主体であるところ、民有林への参入を検討し、より幅広い森林整備能力の獲得を目指す。
進捗状況
令和6年度の間伐事業量185.57ha、生産量7,150㎥程度を実施。
100ha以上の間伐量は昨年も維持できた。
全体の生産量は10,500㎥程度で大幅に減少しているが、これは大雪の影響と下請け業者が独立したことによる。
新規の現場作業員の確保と教育を推進し、この取り組みが軌道に乗れば生産量は回復する見込みである。
令和7年度には人材育成部の立ち上げを行い、新規雇用者に徹底した安全教育を行っている。
(令和7年7月31日報告)
重点的な取組2
- 社会
内容
若手社員を積極的に雇用し、地域の高齢化緩和に貢献する
2030年に向けた指標
40歳未満の新入社員を3名雇用する
進捗状況
令和6年度の新規募集により、2名を令和7年度当初から雇用した。
しかし、令和6年度に発生した重大な労働災害により、安全性に懸念が生じたため、作業者の退職し、現場作業者の人数は横ばいとなった。
労働安全の対策も含め、人材育成部を立ち上げ、継続的に働いていける技能と安全性をしっかりと身に着けてもらえるよう、取り組んでいる。
(令和7年7月31日報告)
重点的な取組3
- 経済
内容
生産性を向上するための新しい技術を開発し、地域林業の競争力向上に貢献する
2030年に向けた指標
架線集材技術を改良し、年間生産量を5000㎥増加させる
進捗状況
欧州製大型タワーヤーダと自走式搬器の利用を推進している。
タワーヤーダを駆使した架線方法の習熟が進んだため、タワーヤーダを使用した現場での生産性が1.5倍ほどに増大している。
将来的に人材5名の確保を行い、民有林での十分な事業量を確保できれば目標を達成できる見込みである。
安定的に生産技術の改善に取り組むためには人的余力が不可欠であり、現在は人材確保と育成を優先して取り組んでいる。
(令和7年7月31日報告)
重点的な取組4
- 環境
内容
架線集材に伴って発生する末木枝条を木質バイオマス燃料に加工して販売することで持続可能なエネルギーの提供に寄与し、
それまで捨てられていた丸太以外の森林資源から利益を得て、森林整備力向上の原資とする。
2030年に向けた指標
南木曽町に中間ヤードの設置及び必要な機械の導入を完了して木質バイオマス燃料チップの生産を開始する。
木曽谷南部(大桑村、南木曽町)全体の未利用材活用を受け持つことを目指す。
進捗状況
必要な機械・車両・人員の確保が完了し、令和6年2月から完全な状態で事業を開始できた。
また、中間ヤードの処理能力が想定以上に高かったので木曽谷南部に加え、木曽谷北部や岐阜県東農地方からの
未利用材の受け入れも行えている。
チッパー機の能力が枝条発生量よりも大きいため、余力を利用して素材丸太の運搬も行っている。
(令和7年7月31日報告)
具体的な取組
最終更新日 2025年07月31日
